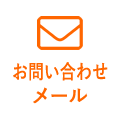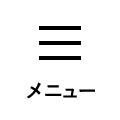新潟特産品
にいがたの味
特産品・にいがたの行事

村には「晴れの日」や「神ごと」と称されるいろいろな行事があります。
季節や農作業の節目に行われている行事には仕事を休み、ご馳走を作って家中で食べ、農作業を手伝ってくれた人にも振る舞ったりして楽しみます。
行事は休養と栄養を補給し、農作業の安全や農作物の豊作を祈願し、村の人々の交流を深めてくれる日になっています。
近年農業や農作業の変化などで影をひそめたものもたくさんありますが、時期や内容を工夫して先代の人々が残してくれた生活の知恵や心をこれからも受け継ぎたいものです。これからもすばらしい生活行事は大切に育み、次代に伝えていきたいと思います。

創業以来、笹は農産加工にとって大切な原材料です。
節句の笹餅、笹だんごの笹、そして「ちまき」には笹はとっても大切。また、保存食としても笹は素晴らしい効能があります。
私達の応援団「笹取り名人」は旧吉川町の道の駅「四季彩」に集う皆さんです。
いつも季節になると素晴らしい笹を用意してくださり有難いです。いつまでもお元気でいてください。
地域の農産加工は農家の「お爺さん」「お婆さん」で成り立っているのです。感謝ですね。
笹だんご

笹だんごは、戦国の頃、上杉謙信と武田信玄の合戦で携帯保存食として生まれたと伝えられています。
最近までは端午の節句の頃になると、どこの家でも新潟では笹だんごを作っていたものです。
辺りに漂う笹と餅草(よもぎの葉)の香りや、軒先に笹だんごが吊るされた風情も今は懐かしい物です。
餅につきこまれた“よもぎ”には食物繊維や各種栄養素も多く、笹には殺菌効果もあり、緑の食品としてはバランスの良い食べ物と言えるでしょう。
越後の気候と風土の中で、先人たちが作った知恵と工夫の結晶が、この小さなだんごの中に息づいています。素朴な味わいをお楽しみください。
養蚕が一段落したとき、”蚕上げ”と言ってどこの家でも笹だんごを作って祝いました。我が家ではあんこが入っていない巻きが主で、おやつとして祖母がよく作ってくれ、私の大好物でした。
(長岡農改・取材先栃尾郷)
笹だんごの作り方
ちまき

現代では「ちまき」は菓子の部類のように考えられていますが、元来は武士の携行食でした。
主食用の米のちまきとして有名なのは「越後ちまき」と鹿児島・島津藩の「あくまき」があります。ともに昔の軍用食料でもち米を用いています。
私達の子供の頃は「おやつ」として、きな粉をつけて食べたものです。
旧節句の六月にちまきを作る。食べ物が傷む時期になるが、笹は殺菌性もあり独特の香りで楽しむことができます。
ちまきの作り方
材料(50個分)

もち米・・・・・・・・・1.5kg
笹の葉・・・・・・・・・100枚
すげ・・・・・・・・・・50本
きな粉・・・・・・・・・150g
砂糖・・・・・・・・・・150g
塩・・・・・・・・・・・少々
作り方
- 生笹の葉は、きれいに洗って水気をきる。
- もち米は、きれいに洗い水をきっておく。
- 笹を1枚中表にして三角に曲げ、(2)のもち米をつめる。
もう1枚の笹でフタをしすげで結ぶ。
5個づつ束ね、10個1組にする。 - 3.のちまきを1晩水に浸しておく。
- 大きな鍋を用意し、ぬるま湯から入れる。
時々水を差しながら弱火で2時間煮る。 - きな粉、砂糖、塩少々を混ぜ合わせ、つけて食べる。
乾燥笹を使う場合、熱湯の中に入れ、もどしてから使う。
ちまきができるまで






梅干し
福井産のぽたぽた梅です。
夏の土用干しをして美味しくと評判の自信作。

昔ながらの着色料や保存料一切なしの
農家手作り「梅干し」
今年も6月27日 梅干しが福井から入荷しました。今年も梅干し作りがスタートです。
最初の仕事が芯取りです。友達が訪ねて来て手伝ってもらいました。
まずは塩漬けにして梅酢を出しました。今年の梅は上作です。




これがしそ!


長かった7月の雨。ようやく梅雨が明けて、8月!天日干しです。
夏場の大切な仕事です。この色が美味しい「しそ餅」の源なのですよ。





かきもち

材料
- 新潟県認証のもち米
- 特別栽培米
- こがねもちで搗いたお餅
かきもちの作り方
こだわりかきもち
白・豆・草・しそ・ごま・のり・あわ・きびなどのお餅をカットして、乾燥かきもちの基を作ります。

乾燥
均一に乾燥することが良質な揚げかきもちの必須条件。
温度管理が決め手になります。
揚げる
カラッとした油臭くないかきもちにするには高温に向いたフライヤーを使います。
米油100%の油で揚げますますから厨房内も気持ちがいいのが特徴です。




揚げ終わったら天日塩でまぶします。
最後の仕上げですが丁寧な仕事が大事です。
そうでないとせっかくの玄米かきもちが破損してしまいます。

そして丁寧に計量して袋詰め作業に・・丁寧に。